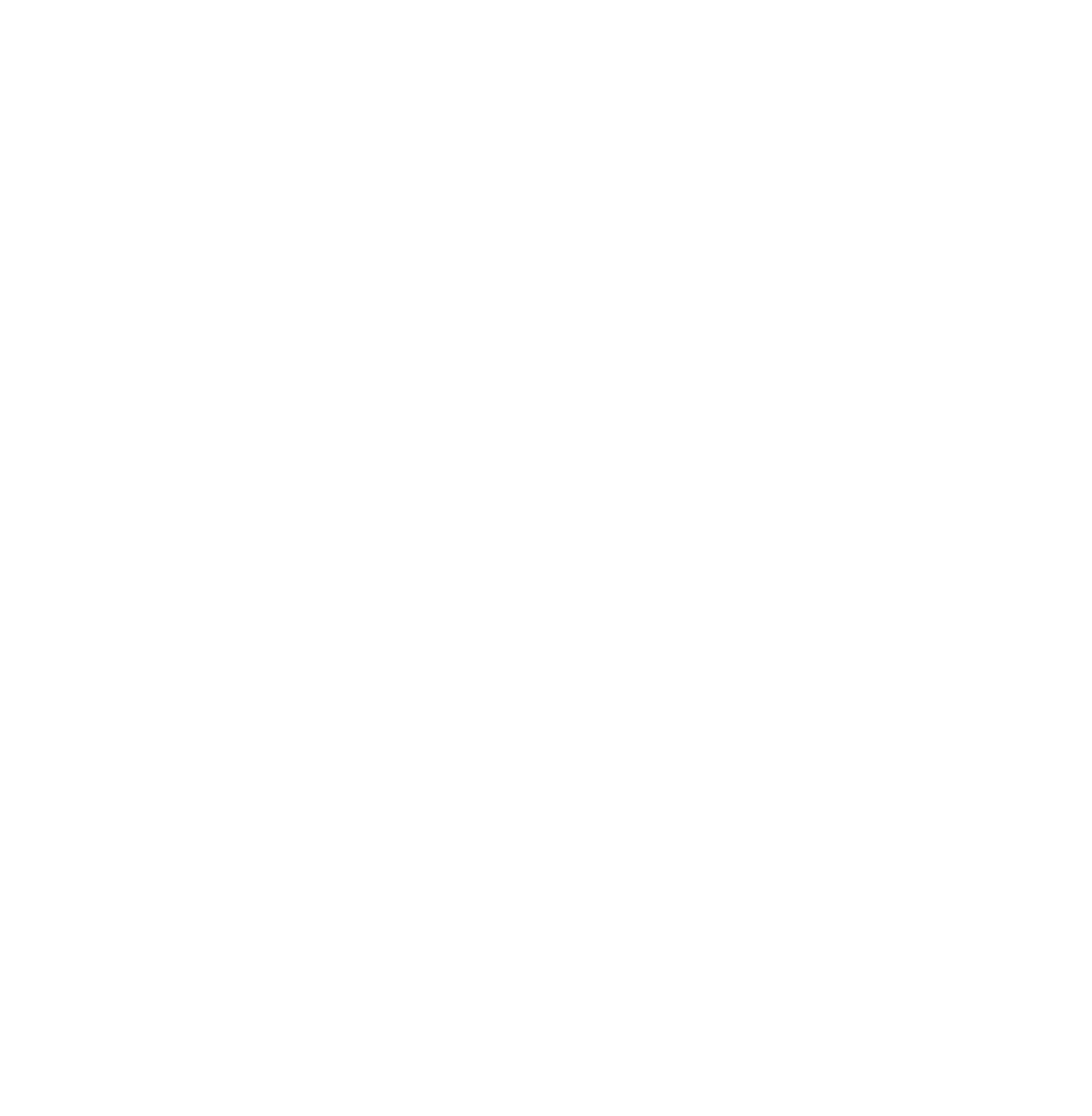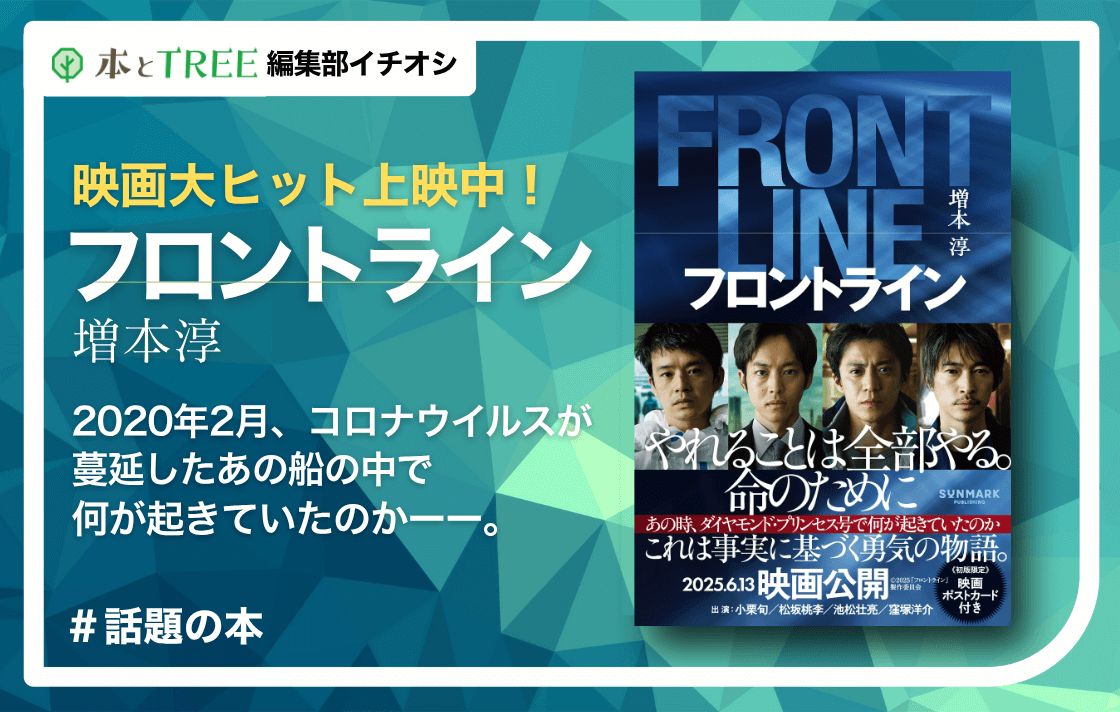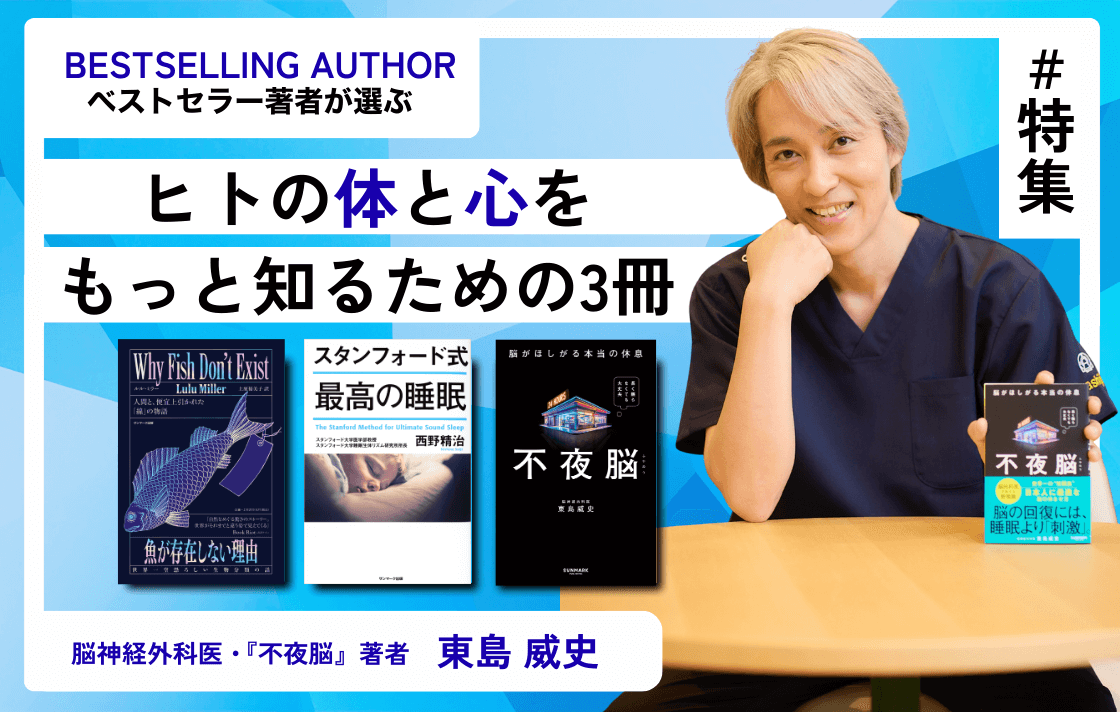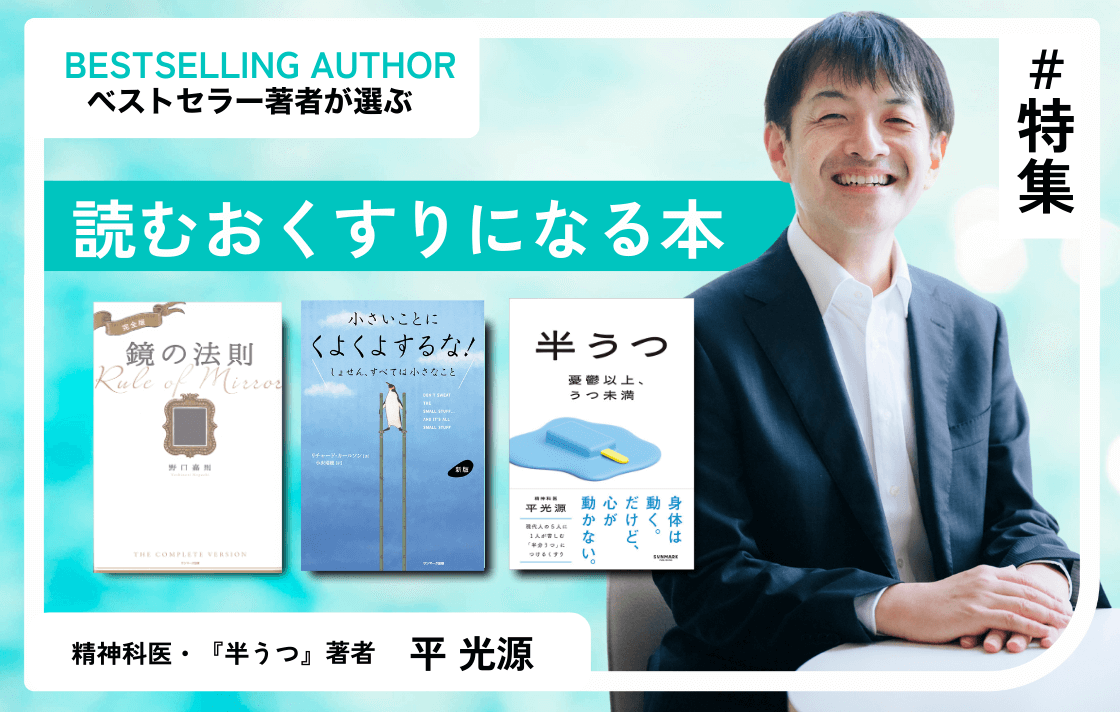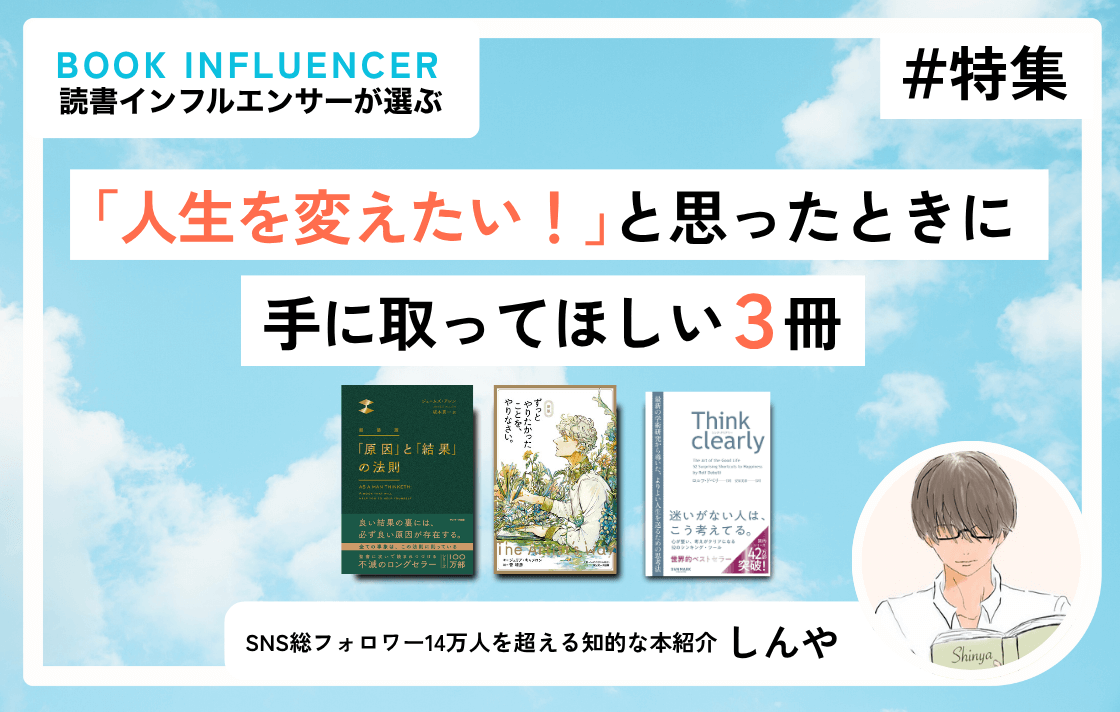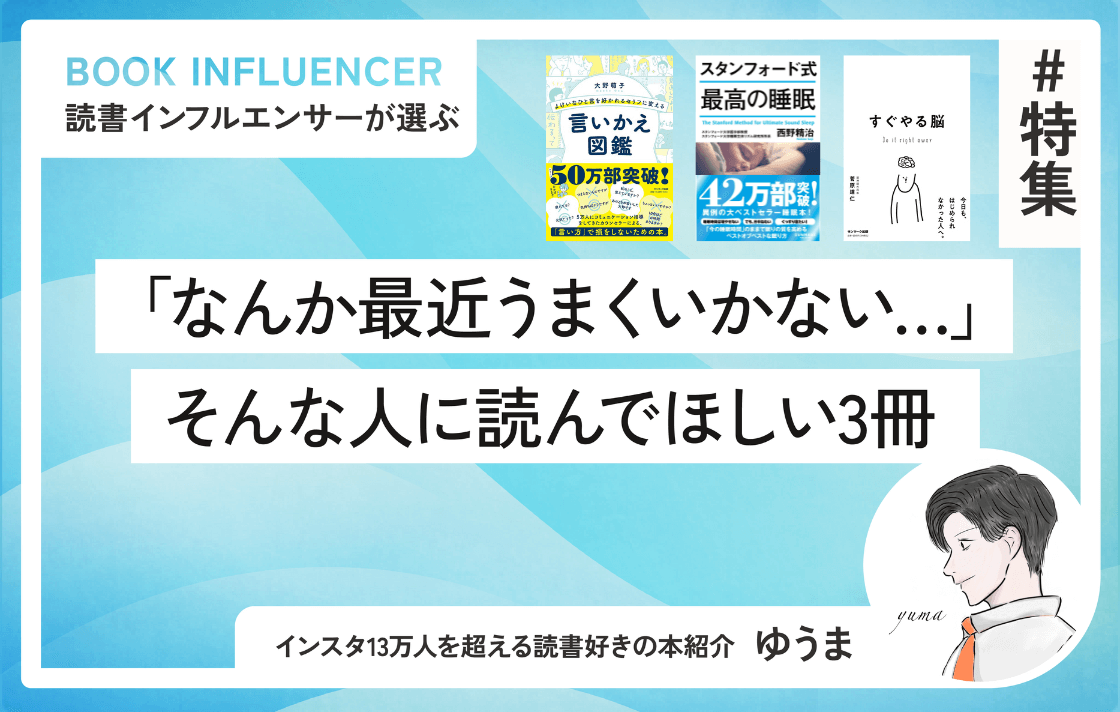考える練習
仕事をしている全ての人に『考える練習』を読んでほしい理由
調達コンサルタントとして活動し、テレビ、ラジオなど数々の番組に出演、企業での講演も行っている坂口孝則さんはさまざまなジャンルにまたがって毎月30冊以上の本を読む読書家。
その坂口さんによる『考える練習』(著:伊藤真、サンマーク出版)のブックレビューをお届けします。
考える練習
演じることで人生が変わる
演劇には、役者が役に完全に没入していく「メソッド演技法」と呼ばれる手法がある。
単にセリフを暗記して演じるのではなく、その役になりきることを重視する。
俳優は自身の人生経験を通して役を解釈し、舞台で自然な行動や感情を表現していく。
時として、役者は演じる役と深く同化することさえある。
「誰かを演じれば、人生なんてすぐに変わりますよ」
先日、この言葉の深い意味を教えてくれた女優に出会った。
彼女は大舞台を終えたばかりで、これから人生の大きな転換点を迎えようとしていた。
「もう、すべてが嫌になってしまったんです」。彼女は語った。
しかし、その声には不思議な確信が感じられた。
私が「これからどうするのですか?」と尋ねると、彼女はこう答えた。
「私は舞台で、希望を捨てずに可能性を追い求める女性を演じていました。
気づかないうちに、生身の私もそうなってしまいました。
これから、可能性を求めて世界に挑戦しに行きます」
彼女は世界各地でオーディションを受けるため、すでに航空券を購入していた。
最低でも1年間は日本に戻らないという。
狭い日本の演劇界にとどまらない、その覚悟に私は心を動かされた。
メソッド演技法の生みの親であるスタニスラフスキーは、演技を通じて人生そのものが変わる可能性を説いた。
彼女の決断は、まさにその理論を体現するものだった。
ビジネスの世界で「発想を変えろ」「まったく違う立場から考えろ」と言われることがあるがなかなか難しい。
普段の発想から逃れられない人は多い。
少し前に、ビジネスパーソンに必要な知識はアートだといわれたが、私はメソッド演劇法こそまさにビジネスパーソンに必要なのではないかと、意外に真剣に考えている。
つねに新しい自分を演じ考え続ける
偶然なことに、冒頭で紹介した女優との会話の後に『考える練習』を読んだ。
私は「つねに新しい自分を演じることによって、思考を強化していく本」だと解釈した。
本書の『第7章「想像力」を広げる練習』にはこう書かれている。
「想像力」、いわゆるイマジネーションの力も、じつは「考える練習」につながる。「想像力」とは自分が見たり、聞いたりしたことのその先を想像すると言うことだから、頭を使って考えないことには成立しない。
(『考える練習』P148より)
電車に乗って、向かいに座った人間になりきって、その人の人生や生活を想像してみるのだ。
着ている服や持ち物の趣味から人となりを考えたり、職業を推測したりする。(中略)
経営者がよくやっているのは、「自分だったらどうするか」「自分だったらどう考えるか」というシミュレーションである。
テレビのニュースやドキュメンタリーで経営破綻した会社や見事復活した会社の話をとりあげていることがある。(中略)
イメージすることは大事である。そこからアイデアが生まれたり、自分に何がたりないか気づいたり、未来像が明確になったり、今何をやるべきかがわかったりする。
(『考える練習』P158、159より)
私はここを読んでびっくりした。
これはまさにマーケティングでいうペルソナの探求と同じではないか。
ペルソナとは理想的な顧客像のことで、具体的に描いていくことで、商品開発やサービス改善につなげていく。
抽象論に陥らず、潜在顧客の誰かになりきって好みを想像する。
まさにメソッド演技法のように、架空の人物と同化することで新しい発見が生まれるのだ。
現代においてマーケティングのセンスを欠いていい人はいない。
なるほど、考える技術とは、生きる技術にほかならなかったのか。
つねに未知の相手と会話をしよう
ビジネスパーソンとして出世して役職がつくとチヤホヤされることがある。
そうすると、急に偉そうになる人がいる。特定の人や取り巻きとしか話さなくなる。
自分を理解してくれたり、忖度してくれたりする人しか会話しなくなる。こうなると危険だ。
一方で、考えるひとは、つねに新しい自分を演じるひとである。
偉そうな立場に安住することなく、いつも自らを磨こうとする。
たとえば内輪の論理や方言(もちろんこれは比喩だ)が通じない世界にも飛び込み論理を鍛える。
共通の文化をもたない外国人と話をしてみると、論理的思考が鍛えられる。(中略)
英語で考えたり、外国人に理由を説明したりすることは、論理的な思考になじんでいく訓練をするには効果があるはずだ。
共通認識や前提がない人に話すときは、論理的でなければ伝わらない。
(『考える練習』P104、P105より)
私はこの記述に非常に思うところがあった。
さっそく、ChatGPTの音声モードを用意して、「アメリカ人で日本文化がまったくわからない役をやってくれ」と説明したら、そのとおりやってくれた。
会話は英語である。これからはアプリを使っても本書が勧める思考練習ができそうだと思った。
私はコンサルタントを生業とし、講演の仕事なども行っている。
私の同業者に「自分の子どもと話しているうちに説明がうまくなった」と語る人がいた。
これは、自分とは異なる存在になんとか理解してもらいたい努力を重ねたからだろう。
分析とは比較することである
つねに新たな人物を演じ、そして、さまざまなバックグラウンドの人と話す。
その過程でどんなことを考えればいいのだろうか。思考をもっと深めるためにどうすればいいのか。
もちろん本書を読んでほしいが、本書を読んで特に気になったところを紹介したい。
「具体的」な経験から「抽象的」な法則やルールが抽出できないと、同じ失敗をくり返すことになる。(中略)
考える力が弱い人には、抽象化が苦手だという人が多い。具体的な出来事は「あれもあります」「これもあります」とたくさんあげられるのに、「だから何だ」という結論が言えない。(中略)
まず「共通点」と「相違点」に注目して、「共通点」の概念を広げていくといい。
(『考える練習』P38、P39より)
「考える」とは、「相互の関係性の種類を見つけ出すこと」だといっても言い過ぎではないと思う。(中略)
そして、それらを見つける一番効果的な方法が「比べる」である。
「比べる」とは、「共通点」と「相違点」を見つけ出すことだ。
(『考える練習』P30より)
帰納的な考え方といえるだろうか。共通していることやパターン、法則性を見つけようとする姿勢そのものが、きっとデキる人間を創り上げるのだろう。
さらに、面白い記述がある。
「あれっ?」と思うほどの極端な意見にふれることが「考える練習」の入り口になる。(中略)
「私は一五〇歳まで生きる」とか「国民には憲法を守る義務はない」とか、とにかく極端な言い方をしてみよう。(中略)その過程で考えが深まっていき、考える力が鍛えられていくのである。
著者の伊藤真さんのような知の巨匠を前に恐縮だが、私は何かを解説する時に「これらに共通することが3つあります。それは……」と言うことがある。
こう言い始めたときには、何も3つの共通点がわかっていない時もある。こう自分を追い込んで戦闘思考力を鍛えるのだ。
すこしだけ昔話をしたい。私は、総合電機メーカーと自動車メーカーで働き、そしてコンサルティング会社に入った。
私が総合電機メーカーに在職中、尊敬する先輩から「分析とは比較することだ」といわれたものだ。重要なのでもう一度言おう。
「分析とは比較することだ」。これは著者の主張にもつながる。
何かを主張するときには、他と比べてそういえるのか、をつねに意識すること。
それだけで相当な思考力が上がるのではないか。世の中の発言の大半は、適当な思いつきにすぎない。
だから、「分析とは比較することだ」をずっと意識してほしい。
話をまとめよう。
思考の最大の敵は同じところにとどまり続けることだ。
だから、新たな自分を演じ続けよう。そして、さまざまな人と出会い対話することが思考力を鍛えてくれる。さらに、具体だけではなく抽象的に考えることが重要だ。
その際には、ぜひ、分析とは比較であるから、自分の考えがつねに他と比べて正しいかを検証しよう。
本書は思考訓練のブートキャンプである。
演劇には、役者が役に完全に没入していく「メソッド演技法」と呼ばれる手法がある。
単にセリフを暗記して演じるのではなく、その役になりきることを重視する。
俳優は自身の人生経験を通して役を解釈し、舞台で自然な行動や感情を表現していく。
時として、役者は演じる役と深く同化することさえある。
「誰かを演じれば、人生なんてすぐに変わりますよ」
先日、この言葉の深い意味を教えてくれた女優に出会った。
彼女は大舞台を終えたばかりで、これから人生の大きな転換点を迎えようとしていた。
「もう、すべてが嫌になってしまったんです」。彼女は語った。
しかし、その声には不思議な確信が感じられた。
私が「これからどうするのですか?」と尋ねると、彼女はこう答えた。
「私は舞台で、希望を捨てずに可能性を追い求める女性を演じていました。
気づかないうちに、生身の私もそうなってしまいました。
これから、可能性を求めて世界に挑戦しに行きます」
彼女は世界各地でオーディションを受けるため、すでに航空券を購入していた。
最低でも1年間は日本に戻らないという。
狭い日本の演劇界にとどまらない、その覚悟に私は心を動かされた。
メソッド演技法の生みの親であるスタニスラフスキーは、演技を通じて人生そのものが変わる可能性を説いた。
彼女の決断は、まさにその理論を体現するものだった。
ビジネスの世界で「発想を変えろ」「まったく違う立場から考えろ」と言われることがあるがなかなか難しい。
普段の発想から逃れられない人は多い。
少し前に、ビジネスパーソンに必要な知識はアートだといわれたが、私はメソッド演劇法こそまさにビジネスパーソンに必要なのではないかと、意外に真剣に考えている。
つねに新しい自分を演じ考え続ける
偶然なことに、冒頭で紹介した女優との会話の後に『考える練習』を読んだ。
私は「つねに新しい自分を演じることによって、思考を強化していく本」だと解釈した。
本書の『第7章「想像力」を広げる練習』にはこう書かれている。
「想像力」、いわゆるイマジネーションの力も、じつは「考える練習」につながる。「想像力」とは自分が見たり、聞いたりしたことのその先を想像すると言うことだから、頭を使って考えないことには成立しない。
(『考える練習』P148より)
電車に乗って、向かいに座った人間になりきって、その人の人生や生活を想像してみるのだ。
着ている服や持ち物の趣味から人となりを考えたり、職業を推測したりする。(中略)
経営者がよくやっているのは、「自分だったらどうするか」「自分だったらどう考えるか」というシミュレーションである。
テレビのニュースやドキュメンタリーで経営破綻した会社や見事復活した会社の話をとりあげていることがある。(中略)
イメージすることは大事である。そこからアイデアが生まれたり、自分に何がたりないか気づいたり、未来像が明確になったり、今何をやるべきかがわかったりする。
(『考える練習』P158、159より)
私はここを読んでびっくりした。
これはまさにマーケティングでいうペルソナの探求と同じではないか。
ペルソナとは理想的な顧客像のことで、具体的に描いていくことで、商品開発やサービス改善につなげていく。
抽象論に陥らず、潜在顧客の誰かになりきって好みを想像する。
まさにメソッド演技法のように、架空の人物と同化することで新しい発見が生まれるのだ。
現代においてマーケティングのセンスを欠いていい人はいない。
なるほど、考える技術とは、生きる技術にほかならなかったのか。
つねに未知の相手と会話をしよう
ビジネスパーソンとして出世して役職がつくとチヤホヤされることがある。
そうすると、急に偉そうになる人がいる。特定の人や取り巻きとしか話さなくなる。
自分を理解してくれたり、忖度してくれたりする人しか会話しなくなる。こうなると危険だ。
一方で、考えるひとは、つねに新しい自分を演じるひとである。
偉そうな立場に安住することなく、いつも自らを磨こうとする。
たとえば内輪の論理や方言(もちろんこれは比喩だ)が通じない世界にも飛び込み論理を鍛える。
共通の文化をもたない外国人と話をしてみると、論理的思考が鍛えられる。(中略)
英語で考えたり、外国人に理由を説明したりすることは、論理的な思考になじんでいく訓練をするには効果があるはずだ。
共通認識や前提がない人に話すときは、論理的でなければ伝わらない。
(『考える練習』P104、P105より)
私はこの記述に非常に思うところがあった。
さっそく、ChatGPTの音声モードを用意して、「アメリカ人で日本文化がまったくわからない役をやってくれ」と説明したら、そのとおりやってくれた。
会話は英語である。これからはアプリを使っても本書が勧める思考練習ができそうだと思った。
私はコンサルタントを生業とし、講演の仕事なども行っている。
私の同業者に「自分の子どもと話しているうちに説明がうまくなった」と語る人がいた。
これは、自分とは異なる存在になんとか理解してもらいたい努力を重ねたからだろう。
分析とは比較することである
つねに新たな人物を演じ、そして、さまざまなバックグラウンドの人と話す。
その過程でどんなことを考えればいいのだろうか。思考をもっと深めるためにどうすればいいのか。
もちろん本書を読んでほしいが、本書を読んで特に気になったところを紹介したい。
「具体的」な経験から「抽象的」な法則やルールが抽出できないと、同じ失敗をくり返すことになる。(中略)
考える力が弱い人には、抽象化が苦手だという人が多い。具体的な出来事は「あれもあります」「これもあります」とたくさんあげられるのに、「だから何だ」という結論が言えない。(中略)
まず「共通点」と「相違点」に注目して、「共通点」の概念を広げていくといい。
(『考える練習』P38、P39より)
「考える」とは、「相互の関係性の種類を見つけ出すこと」だといっても言い過ぎではないと思う。(中略)
そして、それらを見つける一番効果的な方法が「比べる」である。
「比べる」とは、「共通点」と「相違点」を見つけ出すことだ。
(『考える練習』P30より)
帰納的な考え方といえるだろうか。共通していることやパターン、法則性を見つけようとする姿勢そのものが、きっとデキる人間を創り上げるのだろう。
さらに、面白い記述がある。
「あれっ?」と思うほどの極端な意見にふれることが「考える練習」の入り口になる。(中略)
「私は一五〇歳まで生きる」とか「国民には憲法を守る義務はない」とか、とにかく極端な言い方をしてみよう。(中略)その過程で考えが深まっていき、考える力が鍛えられていくのである。
著者の伊藤真さんのような知の巨匠を前に恐縮だが、私は何かを解説する時に「これらに共通することが3つあります。それは……」と言うことがある。
こう言い始めたときには、何も3つの共通点がわかっていない時もある。こう自分を追い込んで戦闘思考力を鍛えるのだ。
すこしだけ昔話をしたい。私は、総合電機メーカーと自動車メーカーで働き、そしてコンサルティング会社に入った。
私が総合電機メーカーに在職中、尊敬する先輩から「分析とは比較することだ」といわれたものだ。重要なのでもう一度言おう。
「分析とは比較することだ」。これは著者の主張にもつながる。
何かを主張するときには、他と比べてそういえるのか、をつねに意識すること。
それだけで相当な思考力が上がるのではないか。世の中の発言の大半は、適当な思いつきにすぎない。
だから、「分析とは比較することだ」をずっと意識してほしい。
話をまとめよう。
思考の最大の敵は同じところにとどまり続けることだ。
だから、新たな自分を演じ続けよう。そして、さまざまな人と出会い対話することが思考力を鍛えてくれる。さらに、具体だけではなく抽象的に考えることが重要だ。
その際には、ぜひ、分析とは比較であるから、自分の考えがつねに他と比べて正しいかを検証しよう。
本書は思考訓練のブートキャンプである。